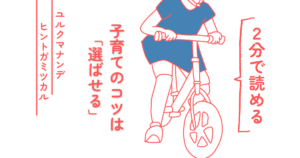「〇〇した方がいいよ」
気づいたら、つい口にしていませんか?
もちろん、親としての助言や経験は大切。でも、子どもが自分で考えて動くチャンスを、知らず知らずのうちに奪ってしまっているかもしれません。
子どもの考える力を育むには、「自分で決める」「失敗して学ぶ」ことが何より大事なんです。
子ども自身の判断を大切に
私たち大人は、つい正解を急いで教えたくなりますよね。でも、それでは「自分で考える力」や「決める力」は育ちにくいんです。
誰かに決められてばかりいると、子どもは自信を持ちづらくなってしまい、何かうまくいかないことがあった時に「どうしたらいいか分からない…」と立ち止まってしまうこともあるかもしれません。
まずは、子どもが自分で判断する機会をつくることから始めてみましょう。
選択肢を与えて自信をつける
「どっちがいい?」と選択肢を与えるのは、簡単で効果的な方法です。
一つの答えを押しつけるのではなく、いくつかの選択肢を見せてあげることで、「自分で選んだ」という実感が生まれ、子どもの自己肯定感も高まりやすくなります。
年齢別 具体的な声かけ例
幼児期
- 「ブロックで遊ぶ?お絵描きする?」
- 「パジャマは自分で着る?お手伝いしようか?」
まずは「どっちがいい?」と選ぶ楽しさから。
学童期
- 「宿題、先にやる?あとにする?」
- 「傘は持っていく?それともカッパにする?」
ちょっとした日常の判断でも、「選ぶ場面」を意識するだけでOK。
思春期
- 「進路はどんなことを大事に考えたい?」
- 「次のテストはどこを重点的に勉強するの?」
正解を教えるのではなく、一緒に考える姿勢が大切です。
失敗は成長のチャンス!
失敗って、実はとってもありがたい学びの種。
- 「なんでうまくいかなかったのかな?」
- 「次はどうしてみようか?」
そう声をかけて一緒に振り返ることで、子どもは自分で解決策を探す力を身につけていきます。
失敗したときの親の役割
共感する
「そっか、悔しかったんだね」
子どもの気持ちを認める。
一緒に考える
「なんでそうなったんだと思う?」
問いかけ、一緒に失敗の原因を考える。
励ます
「大丈夫、次はきっとうまくいくよ」
小さな成功体験を積ませる
「今日、自分で準備できたね!えらいね」
小さな成功体験ができる環境を整える。
まとめ|決める力は、子どもの未来を照らす
日々の「どっちがいい?」「どうしたい?」という声かけが、子どもの考える力や判断力を育てる第一歩になります。
完璧な答えを出さなくても大丈夫。
子どもが自分の力で考え、選び、失敗して、また挑戦していく
そんな繰り返しこそが、子どもの土台を育てるのです。
今日から少しずつ、「自分で決めてみる?」そんな問いかけを増やしてみませんか?